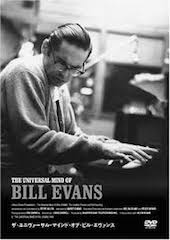小説 ある日曜日(Um Dia de Domingo)
【第22話(エピローグ)】
11月に入り、秋の気配が深まったある日曜日、私はリカルドを表参道にあるシュラスコ(ブラジル風焼肉)のレストランに誘った。その日はジュリアーナがギターを弾いて歌う予定だった。
レストランは自宅の近くにあるので、早めに行ってソーセージをつまみに生ビールを飲みながら待っていると、12時半過ぎにリカルドがやって来た。
リカルドの後ろに、男女の二人連れの姿が見える。どこかで見たなと思いきや、リカルドの愛すべき同僚フリーター君とその彼女のアドリアーナだった。
南米では、誰か一人を招待すると、その友達の友達まで付いて来ることがよくある。まあ、リカルドと二人よりは、若い二人がいた方が賑やかで楽しいし、店の方も予約より人数が増える分には大歓迎だ。
南米流に、リカルドとフリーター君とは握手で挨拶、ガロータ(ブラジルの女の子)とは、またしてもフェロモンに当てられながら頬を付け合う挨拶をした
人数が増えたので、別のテーブルに移動して、全員ゆったりと着席。オーダーはシュラスコ食べ放題のコースと決めていたので、それぞれ飲み物を注文し、再会を祝して乾杯した。
「今日は、ご招待ありがとうございます。彼、日曜日はいつも東京に踊りに来るので、一緒に来ようということになって、ついでにアドリアーナも連れてきました」
「そりゃよかった。今日一日、リカルドは二人の監視役だ。いかにも南米的だね」
「今日の午前中は、彼がいつも踊っている代々木公園という所に連れて行ってもらいました。いや、すごいですね。踊りだけじゃなくて、いろんなバンドや派手なファッションの子がたくさんいて、本当に楽しかったです。フリオさんに連れて行ってもらった所もそうですが、東京には面白いところが多いですね」
「それから、歩いてここに来る途中に、若者であふれた何とか通りとか言う・・・」
『竹下通り』ですよと、フリーター君が解説してくれた。
「リカルドさんもアドリアーナも、何か見る度に ワーとかキャーとか大げさに喜んでくれるんで、案内のし甲斐がありますよ。南米の人は陽気で明るいですよ。この間、文化の日にイベントがあって、二人とも子供たちと一緒にサンバショーに出たんですが、踊っている姿を見ると、やっぱり二人ともブラジル人だなあと思いましたよ」
「僕はあまりうまくないですが、アドリアーナのヒップホップとサンバは本物ですよ。でも、感心して見ていた会社の課長さんを舞台に誘って一緒に踊りだしたのには参りましたけど」
リカルドが「日本人」らしく謙遜した。
「そうか、会社の偉い人も来てくれたのか。これからは職場の雰囲気も良くなるかもしれないな・・・」
楽しく話をしていると、焼きたての何種類ものバーベキューが回ってきた。三人ともすごい食欲だが、やはりリカルドとアドリアーナのブラジル組のペースが速い。私の方は、年のせいか、ビールとつまみだけで腹が膨れてしまい、『肉はもう結構です』を意味する札を、早々とテーブルに置いてギブアップした。
若者たちの腹が満たされた頃に、お待ちかねのジュリアーナがステージに登場した。薄化粧にジーンズ姿のその歌手は、この間どこかのクラブで会った『マリア』さんとは大違いだ。こちらのテーブルに両手で投げキスを送ってくるしぐさは、まさに日本人の顔をしたラテン女だ。
「日本人がブラジルに移住してそろそろ100年だけど、リカルドも、ジュリアーナも、アドリアーナも、日本人の子孫は皆頑張ってるな。本国の日本人ももっと頑張れよ!」
フリーター君の肩を叩いて説教していると、自分でも昼間の酒が効いてきたなと感じたので、黙ってジュリアーナの歌を聴くことにした。
ボサノバが3曲続いたあとは、ブラジルの大物女性歌手ガル・コスタのかつてのヒット曲『ある日曜日(Um Dia de Domingo)』だ。ジュリアーナは最近ずいぶん歌がうまくなって、彼女の透き通った歌声にレストラン中の客が注目して聴き入っている。
『・・・君と座っておしゃべりがしたいな・・・いつかの日曜日のように』
曲の歌詞を聞きながら、リカルドがポツリと言った。
「何か僕の心情を歌っているみたいに感じますよ。この曲、1980年代によく聴きました。あの頃は両親が元気で、三人で楽しく過ごした日曜日が今でも懐かしいです」
「リカルドは、誰かさんと違って、家族の愛情に恵まれて育っただけ幸せだよ」
「木村社長は、相変わらず金儲けに忙しいのでしょうか? 死んだカロリーナが彼に残したメッセージのことは忘れたのかな・・・」
「忘れてないよ。結局、人生で一番大切なのは、金とか社会的な地位がなくなっても、最後に自分に残るものじゃないか。どんな時でも自分を愛してくれるような人は、この世で一番大切にしなきゃいけないよ。木村社長はいつも寂しいから、誰かに愛してもらいたいんだ。でも、人から愛されたければ、自分も人を愛さなきゃ。彼は家族の愛情に恵まれずに育ったから、人を愛することの意味が分からなかったようだけど、カロリーナが命と引き換えにそのことを教えてあげたと思うよ」
酒のせいで、また説教癖が出て来たと思ったので、口を塞いで自重していると、リカルトがポツリと聞いてきた。
「ところで、フリオさん。僕の相談にこんなに親身に付き合ってくれたのはなぜですか?」
「うーん。なぜだろう・・・たぶん、私も木村社長みたいな人間だったからかな」
***
2005年最後の日曜日は、一人寂しく過ごすクリスマスになった。
クリスマス休暇に中国系アメリカ人の婚約者と日本に来ると言っていた息子は、予定を変え、彼女の家族や親戚と一緒に過ごすことにしたらしい。中国系の移民社会では、親族の結束が固く、大事な日には一族で集まる習慣まだ残っているらしい。そう言えば、かつて日本人の移民社会にも、老若男女何世代かが集うそんな習慣があった。
その日曜日も、いつも通り朝寝坊して起き、ソファに座って『木村屋コーヒー』を飲みながらボケッとしていた。BGMをどれにしようか迷ったが、その日の気分には、ケニーGではなく、昔のジャズナンバーであるビル・エバンスの『My Foolish Heart』あたりが似合っていると思った。
人生この年になって、子供だけではなく、年寄りが本当に必要なものも、家族の愛だということに気付いた。
一杯のコーヒーのおかげですっかり目が覚めたので、いつもの習慣でパソコンを開いてログオンすると、サンパウロのセルジオ金城からメールが届いていた。
親愛なるフリオ。日本は寒い冬の季節だと思うが、こちらは真夏のクリスマスシーズンだ。
ところで、今ではどうでもいい情報かもしれないが、一応伝えておく。
木村社長が一週間前からサンパウロに来ている。商談で来ているはずだが、なぜかカロリーナが住んでいたマンションに入り浸っている。
前のメールでも報告したが、そのマンションではアナが、妹のカロリーナと木村社長との間にできた子供ペドロを育てながら住んでいる。美人の姉妹二人とできてしまうなんて、木村という男はまさに日本人の顔をしたラティーノだ。
話は少し複雑だが、東京のブラジル総領事館から自分の死亡届が送付されたため、法的にこの世からいなくなったアナは、これからは妹のカロリーナになり代わって生きていくしかない。つまり、木村社長のかつての恋人アナは、現在はカロリーナと名乗って生きている。おおらかな南米では、何でもありだ。
そして、カロリーナと木村社長の間にはペドロという一人息子がいることになっている。実は俺、本業が暇なんで、例の公証役場に行って、そこの役人にクリスマスプレゼント代わりのチップを渡して、ペドロの出生記録を見せてもらった。両親の欄には、父親「ケン・キムラ」、母親「カロリーナ・サントス」と正式に登録されていて、父親の方は「木村健」と日本語でサインがしてあった。
親子三人は、これから「家族」で楽しくクリスマスを過ごすらしい。
ではまた。フリオにも、楽しいクリスマスとよいお年を!
「家族で楽しくクリスマスか。羨ましいね・・・」
〈FIM〉